振り出し竿の先っぽには、栓がされていてそれを「上栓」とか「口栓」とか呼びます。
その上栓、フィールドで失くしたとき、代替品を探そうにもぴったりのものが手に入らない。純正品は高いし、古いモデルだと廃版になっていることもありうるでしょう。
わたしもよく失くすので、もうこうなったら自分で作ることにしよう、そう思い立った次第です。
動画も作ってみました。ちょっと長いですが飛ばしつつ気になる部分だけ見てください。
失くしがちな上栓

上栓は普段どこにしまっていますか?
私はフィールドに着いたら川面をにらめつけつつ(魚にナメられてはいけません)、まずは糸巻きからラインをすべて出し、毛ばりを口の先にくわえ、上栓を取ってロッドを伸ばしていきます。
取り外した上栓は大抵無意識のうちに上着のポケットやウェーダーの胸ポケットに入れている、はずなんですが、いざ釣りを終えたときにどこにも見当たらない、なんてことがまあまあの頻度で起こりがちです。
なくさないようにするためには、収納する場所を決めておく必要があり、それを無意識にできるようになるのですが、それでも失くしてしまうのが上栓というものだと思います。
まさに上栓は「ありがとうございますぅ。こんなん、ナンボあってもいいですからぁ」的なものです。
単品で買うとやたらと高い

失くして初めて分かることがあります。
それは、純正品以外でぴったりのものを入手するのはとても難しいということ。
メルカリ、ヤフオク、または釣具屋さんでも汎用品を販売していますが、微妙に大きいか小さいかになってしまい、ちょうどよくはまってくれるものはやはり純正品以外には入手しにくいのが現状です。
スッとちょうどよい力感で入り、振ったくらいでは簡単に抜けない、そんな気持ちの良いものは、コンマ1ミリ、時にはそれ以下の精度が求められます。そんなものは売っていないですよね、やはり。
では純正品を買えばいいじゃないかということになりますが、基本取り寄せになりますし、こういったパーツは割引がないので、割高感が否めません。
例えば、今回私が失くしてしまったダイワ清流X45の上栓は、1320円もしてしまいます。価格に見合う品質のものであれば喜んで購入するのですが、実際はゴムの上に木目風の樹脂が付いているだけの簡素なものなのです。
5万円くらいするロッドなら、まあ仕方ないかなとあきらめて買うのでしょうが、ロッド本体が1万円前後だと、上栓だけに1320円はなんか悔しい気持ちになってしまうのは私だけじゃないだろう。
そしてお気づきだと思いますが、上のパーツ表のリンクを見るとこのように表記されています。
ウワセン(11.33MM)
そう、これだけ微妙な寸法じゃないとピタッとはまらないのが上栓なのです。うーん、なかなかシビアです。
これはもう、あれですよ。自分で作るしかないのですよ。ということで今回初めて自分で上栓を作ってみました。
作り方
材の購入

まずはお近くのホームセンター、ネット通販で丸棒を購入します。
制作直径よりも4mmくらい太い丸棒が削りやすいです。今回は上記のように11.33mmのものを作るために、15mmの丸棒を購入してきました。
もちろん仕上げ寸法に近いほど削る量が少なくなるので、手間はかかりません。
今回は近所のジョイフルAKにタモの丸棒があったのでそれを使ってみます。
材料選びのコツですが、針葉樹は木目にそって裂けるのでめちゃくちゃ難しいです。できれば広葉樹を選びたいところ。よく見かけるパインや松、杉は避けたほうが無難でしょう。
広葉樹で木目の間隔が狭く、持った感じが軽いものを選んでください。専門用語で「ぬか目」などと呼ばれていて、そういう材料は家具などよりこういう小物に向いています。
なお交錯木理と呼ばれるラワンもまあまあ削りやすいですが、きれいに仕上げるためにはかなり切れる刃物が必要です。さらにラワンには金筋と呼ばれる部分があるので刃物が傷みがちです。針葉樹よりはマシかも。
削りの順序

まずは先端の木口に完成寸法よりやや小さい丸を書きそれを目安に先端を削っていきます。指を定規にして鉛筆を押さえて、くるっと材料を回せばきれいな円が描けます。これはあくまでもおおよその目安です。
頭部(ロッドから飛び出る部分)との境界も、ぐるっと小刀で切り込みを入れて段差を作っておきましょう。こんな感じ。

そして、やみくもに削っていくと失敗するので、どこを削ったかわかるように削るときはしるし(墨とも言う)をつけておきましょう。しるしが全て消えたら、一周削ったことになります。
またしるしを描いて削って...を繰り返して、とりあえず先端がロッドに入るまで削っていきます。

このように先端だけが入るくらいで一度やめておき、今度は頭部側を少し深めに削っていきます。

出来た膨らみの部分を削り全体がフラットになるように作業を進めましょう。
引き続き鉛筆でくるっと墨を回しながら少しずつ削っていきましょう。最終的に頭側に向かってわずかに太くなっていくような形状にしていきます。
先端が2,3割入るまで削ったらいったん削り作業は中断します。
のこで切れ込みを入れる

薄く目の細かい鋸で切れ目を入れます。これをすることによって、ロッドに入れるときに小さくなり、中で元にもどるのでしっかり密着してくれます。
一番最初にこの切れ込みを入れてもいいのですが、隙間の分グラグラしてしまうので、ちょっと作業はやりづらいかなと思います。なので私は半分が入ったこの段階でやるようにしています。
深さはギリギリまで入れてOKです。
この作業、何気に難しいです。なのでしっかり材を固定して正確に墨付けをしてから作業に挑んでください。おそらく作っても数個なのでジグを準備するほどでもないのですが、心配な人は絶対にミスらない要塞のようなジグを作ってみてもいいでしょう。作ったら見せてください。
全体が入るまで削る

のこで切り込みを入れたら、根元まで入るまで削っていきます。
もちろん無理をしてねじ込むようなことはしてはいけません。固さは各人の好みで良いでしょうが、純正品は人差し指一本で押してするっと入っていく固さですね。
ここで微調整をする方法をご紹介しておきます。
まずはロッドの内側に鉛筆を塗り付けます。そして何度か出し入れをすると、当たっている部分にその塗った鉛筆が濃く付着します。

この鉛筆の色が濃くついている部分を削り、また入れてを繰り返して高くなっている部分だけを削っていくようにしましょう。作業が楽になります。
なお、塗装前にサンドペーパーをかける場合は、それを見越してややきつめの状態でやめておきます。
穴をあける(任意)

ストラップを取り付けたい場合は、切り離し前に穴を開けておきましょう。
2ミリくらいのドリルで正確に加工したいところです。ボール盤をお持ちの方は一発で決まるでしょうが、手持ちの電動ドリルの場合はこれも微妙に難しい作業になります。
片側から通さずに両サイドから掘り進めると失敗は少なくなります。先ほど引いた鋸のラインを延長し参考にすると、裏表がわかりやすいですね。
頭部を成形する

頭部の形状加工は切り離し前にできるだけ済ませておきましょう。切り離すと握ることができず固定も難しいので、加工が難しくなり怪我の可能性も増します。
ストレート形状にするのか、ワインのコルクのような円錐にするのか、もしくは長めにとってなんらかの彫刻を施すのも面白いでしょう。
なおロッド本体との段差を少なくすると見栄えが良くなります。ロッドに装着した状態で削るとはかどりますが、ロッドに傷をつける恐れがあるので、マスキングテープを巻くなど保護を忘れずに。
切り離しと仕上げ

切り離し前にはできなかった頭部の面取り、仕上げ削りをして成形は終了です。
鉛筆の色も付着しているかもしれません。研磨の前に消しゴムできれいに落としておきましょう。
塗装はしたほうがいいと思います。理由はいくつかあります。
- 表面の保護と防汚
- 水分による膨張の防止
特に後者の水による膨張の防止は重要です。塗装をしていないと水を吸いやすく膨張してしまいます。栓をした状態でロッドに残っていた水分に触れて膨張してしまうと、しばらく抜けない、なんてことになりかねません。
塗装をしておくと水分が木に入り込むことをある程度防いでくれます。なお、塗料は塗膜ができないオイルなど浸透性のものにしてください。せっかくぴったりに作ったのに、塗装の厚みできつくなってしまっては元も子もありませんから。
上栓作りは非常に面白い

今回はじめて上栓を自分で削ってみました。
必要な道具は小刀と鋸だけで、ほかに必要ありません。テレビを見ながら、音楽を聴きながら、オフシーズンの冬の温かい部屋でゆっくりじっくり削ってみてはいかがでしょうか。
なお、しっかり研がれた小刀じゃないとうまくいかないと思います。この機会にうまく研げるように練習をするのもいいでしょう。
300mmの丸棒を一本買えば、5.6個作ることができると思うので、失敗しても諦めずに続ければそのうち会心の作が出来上がるでしょう。
頭部だけじゃなくて全体が一つの木でできている上栓は、純正品ではあまり見かけません。やはり木よりも伸縮が少ないゴムの方が製品に向いているからでしょう。
失くしていなくてもおしゃれパーツとして銘木で制作してみてもいいかもしれません。
ローズウッド、コクタン、花梨なんかがよさそうですね。もちろん堅い木は加工も大変なのでよく研磨された小刀が必要になります。







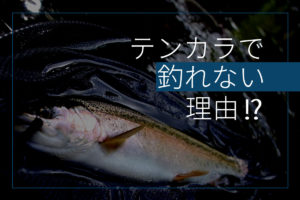

コメント