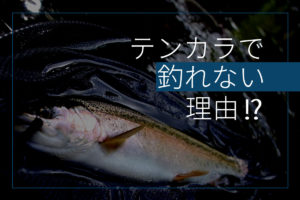先日手元まで寄せた大物にラインを切られて逃げられてしまいました。釣り人がよく口にする話です。やはり、写真を撮ってメジャーで計測をしないと釣ったと人に言えません。
テンカラで大物をねらうようになって、これで3度目です。いい加減この問題を何とかしたいと考えうる対策を挙げてみました。一つずつ検証していきます。
ラインを短くする

普段は4.5mのロッドに6mの仕掛け(レベルライン5m+ハリス1m)を結んでいます。
それを中規模の河川で振り回すのでなかなかテクニックが必要ですが、慣れとは怖いもので何とかなってきます。
この長いラインのテンカラは、一言で言うとめちゃくちゃ面白いので、それをやめる気は今のところありません。やったことがある人はわかると思います。
通常のライン長のテンカラと比べるとかなり遠くまで毛ばりを運ぶことができるので、アプローチの不利を埋めることができ、大物が出る可能性も上がります。
話を戻して、もし仕掛けの全長をロッドと同じにしておけば、ランディングは格段に楽になります。確かにロッドはしなって魚との距離は伸びるんだけど、手をしっかり伸ばせば足元まで寄せることができるから。
だから、仕掛け全長を短くすればするほど、それに比例してランディングの成功確率も上がっていくわけです。でも、先ほど書いたようにゲーム性を犠牲にしなきゃいけない、このジレンマ。
ちょっと話が変わりますが、キャスティングの精度を上げて毎回フルレングスでキャスティングをすることができれば、今より50センチ短くしても魚にはしっかり届くというのも事実です。
だから、仕掛けを見直すことも大事だけれど、キャスティングの練習も同時にすべきなんでしょう。レベルラインテンカラはキャスティングが安定しないのでなかなか難しいんだけど、練習のしがいはあります。
ノット(結び)を変更する

テンカラを始めたとき、いろいろな本を読んで試行錯誤をしつつ、頻繁にノットを変えていましたが、ここ3年くらいは一つの方法に落ち着いていました。こちらに記載の方法なのですが、シンプルで失敗が少ないからせっかちな私には合っていました。
だが、よくよく思い返してみるとひとつ気がついたことがあります。それは、切れるポイントが7:3くらいでレベルラインとハリスの緊結部分だということ。毛ばりを結んでいる部分はあまり切れない印象です。
いずれにしても、1.5号のナイロンを使うようになってから途中で「ちぎれる」といった切れ方はほとんど見なくなりました。やはり、ラインブレイクは緊結部分のこぶで発生しがちです。
なので、レベルラインとハリスの緊結方法を見直すことにしました。結果は追ってご報告いたします。
柄が長いランディングネットを使う

ラインを切られるたびにちょっと頭をよぎるのですが、もうちょっとランディングネットの柄が長ければうまく掬えてたんじゃないだろうか、と。
今使っているネットは全長で言うと渓流釣りに使うものとしては比較的大きなもので、普段使いにはサイズ、デザインともにとても満足していますが、大物のランディングに際しては若干短く感じます。この商品です。
あと50センチ長ければ、先日の大物も、去年のアイツもしっかり手中に納まっていたかもしれない。
当たり前の話だけど、柄が長いランディングネットは持ち運びが大変になります。
理想的には、立った状態腕を伸ばしてネットの付け根(柄の先端)が水に浸かるくらいの長さがあると、ランディングの姿勢はかなり楽になって、失敗も少なくなると思います。
そうなると柄の長さが600mmくらいほしいところだが…この商品なんかよさそうです。でも、大物とやり取りしている最中に、たたんだ柄を伸ばすのは大変そうだ。
とりあえず、今使っているネットの柄を交換するか、新しいものを購入して試してみようと思います。こうしてどんどん、私のテンカラは本流寄りの装備に代わっていくのでしょうか。
ハリスを太くする

いま使っているハリスは1.5号です。
大きなトラウトをねらうものとしては標準的だと思いますが、それはあくまでもドラグがある釣りでのことで、延べ竿での釣りとしては細いほうかもしれません。
大物かつ豪快に走る鯉釣りのハリスは4~6号らしいので、40センチ以上のニジマスをねらう私の釣りでも少し号数をあげてもよいのかもしれませんが、ハリスを太くすると当然切れにくくなるので、今度はロッドが折れないか心配になってきます。
今のシステムにしてからランディング時以外ではラインブレイクを起こさずに何とかやり取りできているし、魚にもバレていないと思うので、仕掛け全体のバランスはそこそこのものだと自負しています。
2号を試してみてもよいかもしれないが、試した結果が「ロッドが折れました」となる可能性が高くておっかないのです。現状でも相当ロッドには負担がかかっているはずです。ギュンギュン鳴りっぱなしですから。この緊張感が最高に面白いんですけどね。
追記:太くした結果
先日、2号のハリスを結んだ状態で50弱のニジマスをかけました。順調に手元まで寄せた直後、本気で走られ、ロッドのしなりの限界に達し(感覚的にはロッドがただの硬い棒になった感じ)、数秒後にラインが切れました。
ということで、今使っているロッドのハリスの太さの限界は2号か2.5号といったところでしょう。あと数秒ラインが切れずにいたら、ロッドが折れていたでしょう。
切られた直後にロッドの変更を考え始めました。やはり北海道でニジマスをねらうとなると相当パワーのあるロッドが必要になります。もちろんその分重たくなって、一日中振り続けるテンカラにとってはかなり不利になってしまいます。
テンカラロッドとして実用的な長さの限界は、重さ的に4.5だと思います。その長さで軽くてパワーのあるロッド、と考えると、必然的に鯉竿にたどり着きます。
近いうちに一度試してみるつもりです。なんだか面白くなってきました。
ランディングの方法を変える

ラインが長い場合はラインを手で手繰って全長を短くしてからランディング動作に移ることになりますが、このラインを手繰って手に持っているときに魚に再度走られると、その時に瞬間的に切られることが多いです。
ラインの長さを変えないという前提でランディングの方法を変えることは可能なのでしょうか。
もし河原が広ければ、自分が後退して無理やり河原に魚を引きずりあげてしまうという方法があります。もちろん魚へのダメージが大きくなる方法なのでなるべく避けるべきではあるのですが、ランディングに失敗し魚の口に毛ばりをのこしてしまうよりはましだと思うので、この方法は可能であれば(広い河原があれば)取りたいです。
もう一つは、ネットが完全に水につかるまで自分が膝くらいまで川に入ってネットを構えて、魚を誘導しつつ泳いでネットインしてくれるタイミングを探るという方法です。浅いところで魚に暴れられるよりもラインブレイクの可能性は減るはずですが、果たしてうまくいくのだろうか。
私はいままで浅瀬に魚を寄せてランディングネットを構えるというのが取り込みのデフォルト動作だという固定観念のもと行っていましたが、これも一度考え直す必要がありそうです。
同行者に掬ってもらう

これも実は有効な方法だと思っています。そもそも論なんですが、釣りもあらゆる面でワンオペよりも有利なんです。
でも、手元まで寄せた魚は、人の気配を感じるともうひと暴れする傾向があるので、それが自分でも他人でも同じなわけで、どうなんだろうか。同行者はロッドを持っていない分、自由に動けるので成功の確率は高くなるとは思っています。
でもだ、この方法の最も怖い部分は、失敗したときの責任の所在だろう。
口では「いやいや、仕方ないですよ」といいつつ、心の中では「自分でやっておけばうまくいっていたかも!」と考えてしまうかもしれず、それをずっと、へたすりゃ一生考え続ける可能性もあります。
※私と同行する人は、私から頼まれてもランディングの代行は断ったほうがよさそうです。
加えて、やはり自分でランディングをしてこそ釣り上げた!と言うことができる、というお考えをお持ちの方も多いと思います。私もできるなら自分でランディングをしたいです。べつにマグロ釣りをしているわけでもないので。
まとめ:フライ・ルアーへの転職は避けたい

大物のランディングに失敗したとき、必ず帰りの車の中でルアーだったらあのロッドにあのリールをつけて…とか、フライだったらあのメーカーのロッドがよさそうだなぁとか、そんなことを自然と考えてしまいます。
要するにドラグが存在する釣り方への転向ということです。
そもそも、なんで自分がテンカラをしているか、それを思うとこの考えはすぐに消えてしまいます。理由は簡単、テンカラがオモシロイからです。そして、環境への負荷がほかの釣りに比べまだマシだから。
フライもルアーも、リールを使用しドラグ機能があるので魚の急激な走りに対処することが可能ですが、それでもラインを切られることは多々あります。それだけランディングって難しいものなのです。
だから、ラインの長さを調整できず、かつドラグ機能もないテンカラは、ランディングがめちゃくちゃ難しいことがわかると思います。裏を返すと、それだけうまくいったときの喜びは大きくなります。
話のなかでも触れましたが、魚が泳いでくるその方向にネットを構えて自然にネットインさせるというのが理想的で、そこまでの準備を私がうまくできるかがカギになりますね。道具面、動き面ともに精度を上げていきたい。
ここまで解決策について自分なりにあーだこーだ考えてきましたが、ちょっとの違い、例えばランディングネットの全長を10cm伸ばし、仕掛けの全長を50cm短くする、それでもランディングの成功率は変わってくるでしょう。
これからも経験を積んでちょうどよいバランスを探っていきたいです。