ジャン=ジャック・ルソーが書いた「エミール」。
今日まで教育学の名著とされています。まだ読んだことがない方へ、その概要をかいつまんで説明してみたいと思います。
私は社会人になってから通信制大学で学び、哲学と文化人類学の授業を主に選択しました。その過程でルソーも学びなおしたというわけです。一緒に「エミール」という不思議な本をのぞいてみましょう。
「エミール」はこんな本です
ルソーが架空の男の子「エミール」を育てるお話。かなり斬新ですよね。あの変態ルソーが教育なんて…
ちなみにルソーは保育園の先生でもないし、子育てに関心もありませんでした。むしろ、自分の子供は5人とも孤児院に預けてしまったほどです。
当時の習慣だったとは言え、この後悔もエミールを書いた動機の一つになりました。
ではなぜ、子供に無関心だったルソーが急にこんな本を書いたのか?
そこを理解できていないと、ただのフィクションになってしまいます。この本を書くにあたりルソーが考えていた二つのことがあります。
「エミール」には2つの大前提があります

ルソーが執筆にあたり考えていた二つの重要なことがあります。それらを理解していると、この本を読んだ時の理解が一層深まります。
- 社会は堕落している
- 人間は本来、善の存在である
では、以下で一つずつ見ていきましょう。
社会は堕落している
これは今も昔も変わらないことかもしれませんね。
ルソーが生きた近世フランスも王家、貴族、聖職者ら特権階級が富を独占し、人口の9割を占めていた平民は重税に苦しんでいました。(アンシャンレジームというやつです)
そして、それら特権階級の生活は堕落していました。暴飲暴食、賭博、ふしだらな性生活、やりたい放題、めちゃくちゃだったようです。
そんな間違った社会の中で、平民に正しい知識を与えようと啓蒙主義(百科全書派)にルソーは傾きますが、こんな風に考え始めます。
間違った社会が作る知識は正しいのだろうか?
そもそも論というやつですね。
第二次大戦期の日本もそうでしたが、国家がそもそも間違った方向に進んでいる場合、その中で作られた教育システムも間違っているかも、と考えるのは自然でしょう。
ということで一つ目のポイントは「今の社会は堕落している」でした。これを前提にして話は進みます。
人間は本来、善の存在である
性善説、とは少し違うかもしれません。性善説とは年齢を問わず、人間は善の存在であると定義することです。
ルソーがいう善とは、生まれ落ちた瞬間は善だったというとらえ方です。
大人になるにつれ、堕落した社会の中で育っていくので、善であった人間も性根が腐って堕落していくと考えました。
そもそも、人間は生まれた時は善も悪も知らない、無垢な状態で生まれてくる。だから、周囲の環境がまっとうな状態であれば善を伸ばして大人になれるということです。
余談ですが、ホッブズという哲学者は反対の考えで、人間は本来悪で放っておくとどうしようもないので、秩序を保つためにはある程度の押さえつけが必要だ、と考えました。
あなたはどう思いますか?
でも、ルソーもすべてを放任しろとは言っていないので、真っ向から対立する関係ではないのです。これから述べますが、ルソーが考えたのは押さえつけの教育ではなく、ひたすら寄り添う教育だったんです。
少し脱線しましたが、二つ目のポイントは「人間は本来、善の存在である」です。
ルソーは実際にエミールとどう向き合ったのか?

先ほどの大前提2つは理解できたでしょうか?
だからこそ、理想的な教育環境で無垢の子を育ててみようという実験なんです。
この前提そのものがおかしくない?という意見も当然あると思います。ですが、それはいったん置いておいて、この空想の教育の中身をのぞいてみましょう。
いかに本来の善を保ちながら、汚れた社会から距離を置き、慎重に育てていくかがこの本の肝心な部分になります。なのでかなり細かく指示がなされています。具体的にいくつかの項目に分けてみていきましょう。
自然と田舎暮らし

エミールはどのような環境下で育てられたのか?
一言で言うと「田舎と自然」なんです。これは超大事なキーワードです。
ルソーの思想の大半はこのパワーワードで説明できてしまうのですが、それを言ってしまうとここで話が終わってしまうのでもう少し続けます。
ルソーは普段から自然が大好きでした。ここでいう自然は、森や川といった自然だけではなく本能だったり先天的なものだったりも含む、大きな意味での自然です。
先ほども述べたように、その人間に備わっている自然の一つが「善」だということです。
エミールを教育するために必要なものは田舎の生活で手に入るもの、すなわち、「自然、周りの人、周りの物事」だとルソーは主張しました。
自然に育てることは、ある程度は放っておくことを意味します。幼いころからしつけや教育を与えるのではなく自由に行動させることをよしとしました。
でも大切なことは、「良好な環境で」自由にのびのび育てましょうということ。スラム街や犯罪がはびこる街で自由に出歩くようになると、必ずその街の雰囲気に染まっていくものです。
知識よりも体験を重視

ルソーは、農村や技能集団といった人間が本来する営みの中で自由に育てましょうと言いました。先ほどもお話しした「田舎」ですね。
森や川などの自然の中で心ゆくまで遊び、ある程度成長したら、今度は農作業や職人のもとで技術を学ぶ。それらを通して、知識よりも先に五感を鍛えてあげましょうと言っています。
自然科学に関しても、教科書で教えるのではなく実際に外へ連れ出し、疑問を投げかけて問答をします。自分の頭で考えて自分なりの結論を出していく訓練をするわけです。
「徹底した現場主義、フィールド主義。それができるのは田舎」というのがルソーの主張の根幹です。
子どもに支配されない

子どもが泣くのは親をコントロールするため。
だから、泣いていてもすぐには近寄らない。これは現在の教育でも通用する考え方ですよね。小学生になっても泣きわめいているようでは、残念ながら周囲の育て方に問題があった、ということになってしまいます。
泣くことには何の意味もないことを教えなくてはいけません。いちいち周囲がリアクションをしていては、自分を憐れんでほしいというゆがんだ自己愛を植え付けてしまいます。そうルソーは述べています。
愛情とは毅然とした態度を示すことにほかなりません。この時代にここまで観察しているのはさすがルソーといったところ。
嘘という言葉を教えない

ルソーはウソという概念にも言及しています。
子どもが嘘をつくようになってしまったら、教育する側に問題があったということになります。嘘は罰を逃れるためにつくものだからです。
もし子供が何かを壊してしまった場合は叱るのではなく、たんたんと片づけをすればよいだけです。
叱るまでもなく、子供は自分がしてしまったことを知っている(本来善だから)ので、謝罪し行動を改めるのを辛抱強く待てばいいだけだよ、と述べています。
そういう環境下で育った子供は「嘘をつく」ということがそもそもわかりません。だから、小学校に通うようになって、ほかの子が先生や友達に対して嘘をつく様子を見て不思議に思うわけです。
この嘘を知らない状態は言い換えると、常に素直であると言えますね。自然の中で五感を育て、起こった物事はそのまま受け入れ、叱ったり押さえつけたりしない教育者に守られながら素直に育って、初めて学校教育を受ける段階になるとルソーは書いています。
知識がなく素直だと、知らないことは知らないと言えます。
学校教育の前段階として必要なことは、「嘘が必要のない生活の中で素直さをはぐくむ」ことなのです。
本を読ませること、体を使わせること

教育の初期の段階では、本を読ませる、特に自伝や伝記をルソーはすすめています。
生身の人間は狡猾で薄っぺらく偽りが多いものです。過去の偉人の自伝や伝記は真実の気持ちが率直に語られており、そこには美化も残酷もありません。歴史的な大事件ではなく、人間の些細な行動をリアルに感じることを通して、自信を見つめなおし、幸福への道をさぐるのです。
いくら偉大な人間でも、他者を前に言葉で語るとそこにはいくらかの取り繕ったものが混じってしまい、ほんとの感情は吐露できません。自伝だとダイレクトな感情を知ることができ、共感、同一視ができ、自分は他人とそんなに違わない、どんな偉人でも同じようなことで悩むし自分もなんら特別ではない、ということに気が付くことができます。
青年期になったら読書と同じ時間を肉体労働に充てて少しづつ社会になじませます。体の疲れは精神の訓練で癒す。精神の疲れは体の訓練で癒す。という大切なことを習慣として身に着けます。
健全な自己愛と他人を大切にする気持ち

ルソーは青年期になるまでは徹底して、エミールに社会の汚い部分や負の側面を見せずに育てます。理性と判断力が身に着くまでは、徹底的に不徳から遠ざけ守る態度です。過保護ともいえるかもしれません。
ここまで述べてきた教育がきちんとなされて、嘘がない健全な自己愛
、そしてそれがあふれる形で現れる他者への愛
、それに加えて五感とたくましい肉体
、それら準備が十分に整ってから、はじめて社会に出すのです。
ここではじめて社会の不合理にふれさせ、過度の期待や自信とうまくバランスを取り、スポーツや音楽、勝負事などで負けることを通じて、自分を守ることも知り、幸福になる道を考えさせるのです。
熾烈な競争、残酷な現実などには、準備ができてから対峙させましょう、ということです。
宗教との向き合い方は?

読書や社会での教育も無事に済んだら、次に宗教について考えなくてはいけません。ルソーは宗教について、必ずしも必要だとは断言しませんでした。自分で判断して自分で選べと書いています。
牧師が「神は存在する」と言うから、家族がそうだからという理由で、不確かなものを信じてしまうのはいかがなものかと言及しています。
でも、自然の中で育ったエミールは、自然の中に何らかの神が宿っているということを身をもって知っているはずで、最終的に自然という神を信仰するでしょう。
自然信仰、日本で言う八百万の神、世界中の原始宗教に見られるもので、それらは人間の権力や欲とは切り離された、怖れと敬いから生じる純粋な信仰です。
さて、ここまでくると、もうすぐルソーによるエミールへの教育は終了します。
異性にはどう接したらよいのだろうか?

エミールに最後に残された課題は良きパートナー選びです。ルソーの指導は徹底してますね。まぁ、空想なので可能なことなんですが。
ルソーとエミールはソフィという理想の女性を定義し、その人を探し求めて旅をします。ついに自分と同じような「善の存在」である女性(ソフィー)と巡り合うことができますが、ルソーはあえて、一度エミールをソフィから引き離して、喪失とそれに立ち向かう勇気を教えます。
ここまで順調に育っていても、まだまだ教えることはあったのです。
そして、ルソーの助言に従いしばらくエミールはソフィと離れて暮らし、自分が幸福になるための準備ができた後、二人は再会し改めて一緒に生活を始めるのでした。
めでたしめでたし、、、なのでしょうか? エミールのその後が気になる方はこちらの記事もどうぞ。多くの人が知らないエミールのその後
まとめ:エミールへの教育は終わりました

以上が、ルソーがエミールにしてあげたことです。
そして、ルソーはこの本のなかでは放任ではなく、いつもエミールのそばにいて献身的に教育をしました。どんな出来事も感情も共有しようと試みています。もちろん、あくまでも空想の話ですよ。
子どもを育てたことがない人の話なのですが、特に乳児~幼児期の向き合い方は、現代の子育てでも十分通用します。今から250年ほど前に書かれた本とは思えないくらい、教育しかり、幸福論しかり、宗教への向き合い方しかり、とても現代的な考え方ですよね。あと観察力が半端ない。
ルソーが進んでいたというより、人間の本質は時代を経ても変わらないと言ったほうが正しいかもしれませんね。
最後におさらいです。
「エミール」はルソーの考える理想的な教育を書いた本です。書かれていることを要約すると、社会(都会、貴族社会)は堕落しているから、それらを避けて子どもを田舎で育て、本来人間が生まれたときに持っている善を損なわないように慎重に教育をする。
今回はここまでです。最後までお読みいただきありがとうございました。







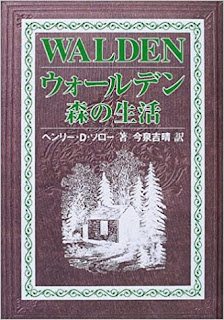
コメント